トップページ > 施策のご案内 > 万博・SDGs > SDGsの推進 > 企業のSDGs取組事例(SDGs貢献ビジネス) > 株式会社日吉
『はかる、みる、まもる』環境サービスを通じ、国を越えて、人の生活と産業の最適化を実現する
~株式会社日吉~
最終更新日:令和5年4月3日
「はかる、みる、まもる」を実現する環境サービスを通じて、水質・大気・ダイオキシン類などの環境試料から化学物質や食品栄養成分等の測定・分析、上下水道インフラ施設や道路等の維持管理、廃棄物処理や工業薬品販売といった様々な分野で事業を展開する株式会社日吉。同社は科学的な根拠に基づく対策・提案のできる環境総合企業となることを目指しています。
今回は、村田社長はじめ、同社で海外・新規事業を担当される松井室長、黄課長、総務部より広報的観点から大角課長、赤塚さんから、海外と深い関わりを作ることになったSDGsの取り組みについて、お話を伺いました。
◇企業情報
企業名 : 株式会社日吉(滋賀県近江八幡市北之庄町908番地)
代表者 : 村田 弘司
創業年 : 1955年
(概要)
人の生活環境が快適に、また産業活動が最適に持続可能となるよう社会の課題や問題に対応する環境保全サービス事業を展開。1980年代からインドやベトナムなど世界36カ国から累計1000名以上もの研修生を招いて環境の大切さを伝えることで、現地の環境問題を認識してもらい、当社が国を越えてビジネス展開を図る機会につなげています。
1.インタビュー
SDGsに向けて、どんな取組をされているのですか?

当社は、人の生活環境が快適に、また産業活動が最適に持続可能となるよう社会の課題や問題に対応する環境保全サービス事業を展開しています。
創業以来、生存権を定めた憲法第25条の実現を事業の根拠に据えて、環境関連法令に基づき、大気中や水、土壌の汚染物質や食品中の残留農薬等を測定する『はかる』事業、上下水道施設や廃棄物処理場などの施設を管理・モニタリングし、日常的な異常対応を行う『みる』事業、そして廃棄物の収集・運搬や工業薬品販売など、地域や工場インフラの管理保全を行う『まもる』事業という3つの事業を柱に、生活環境の保全や公衆衛生の増進に努めています。
当社では「環境」をテーマにインドやベトナムなどの海外大学生と交流を図っており、会社の特徴の1つになっています。
インドとのつながりは、当社の前会長とインドのABK-AOTS DOSOKAI, TAMILNADU CENTREの会長Ranganathan氏との個人的な繋がりから始まりました。1995年からインドにおいて環境問題をテーマにしたスピーチコンテストを、当社がスポンサーになり、開催しています。優勝者は副賞として日本に2週間招待し、滞在期間中に、当社が携わる水処理施設等の見学や分析技術を学び、日本文化を体験してもらいながら環境について意識を深める研修を行っています。当社の技術を使ってインドの水をきれいにするためには、まず“環境は大切”であることを現地の人々に知ってもらうことから始めなければならないという思いで今日まで続けています。このスピーチコンテストは、これまでに総数4000名程の応募があり、環境関連技術を学びたいという意欲を持つインド人を延べ100名以上日本に招待しています。
こうした取り組みはその後の現地事業につながっています。これまでインドから多くの研修生を受け入れてきましたが、当時のインドはまだ環境に対する意識が低く、彼らが自国に帰っても学んだ知識や技術を活かす場がありませんでした。そこで2011年に当社初の海外子会社としてインド・チェンナイに日吉インディアを設立。研修生の中から6名が採用に至り、うち優秀な人材1名を取締役に抜擢し、水質分析や水処理事業を展開しています。当社で学んだ研修生達が、当社のインドでのビジネスを支えてくれています。インド・チェンナイでは、元研修生達が自発的に発起した『日吉同窓会(HIYOSHI-Alumni)』から、現地の大学や学識者にもつながり、ネットワークが広がっています。
現在、ベトナムの人材も高度人材として日吉で活躍しています。JICA草の根スキームを活用した、ベトナム ハイフォン市カットバのグリーン成長の基盤づくりを滋賀県と当社もメンバーとする共同体で実施し現在フェーズ2を行っています。滋賀県が産官学民連携で琵琶湖をきれいにしながら経済発展させてきた『琵琶湖モデル』の仕組みと経験を導入して基盤を作り、現地の環境意識の高まりにつながり、やがては当社の新たなビジネス機会になればと考えています。その際には、当社で学んだベトナム人インターン生が活躍してくれるものと期待しています。
このような海外事業に取り組む一方、企業として長く持続することも重要です。そのための一つとして、社員の柔軟な働き方を受け入れられる社内環境の整備も進めています。きっかけは2014年にある女性社員から、「育児をしながら長時間通勤するのが難しい」との理由で退職の意向を示されたことです。当社ではそれまで在宅勤務制度がなかったのですが、これを機に導入しました。他の社員との公平性を保つという問題もありましたので、彼女には正社員からパートに雇用形態を変更してもらい、また情報セキュリティ確保の課題等も一つ一つクリアしながら進めました。
後にこれが好事例となり、コロナ禍ではスムーズにテレワークを導入することができました。当社には現場の作業員もいるので、全ての社員がテレワークできるわけではないのですが、現在も公平性に配慮しながら機会の平等性に重点を置き、感染防止対策と並行してテレワークできる範囲と付加価値を広げようと努めており、最近では育休中の男性社員の在宅勤務も実現しています。

SDGsの取組をはじめたきっかけは?
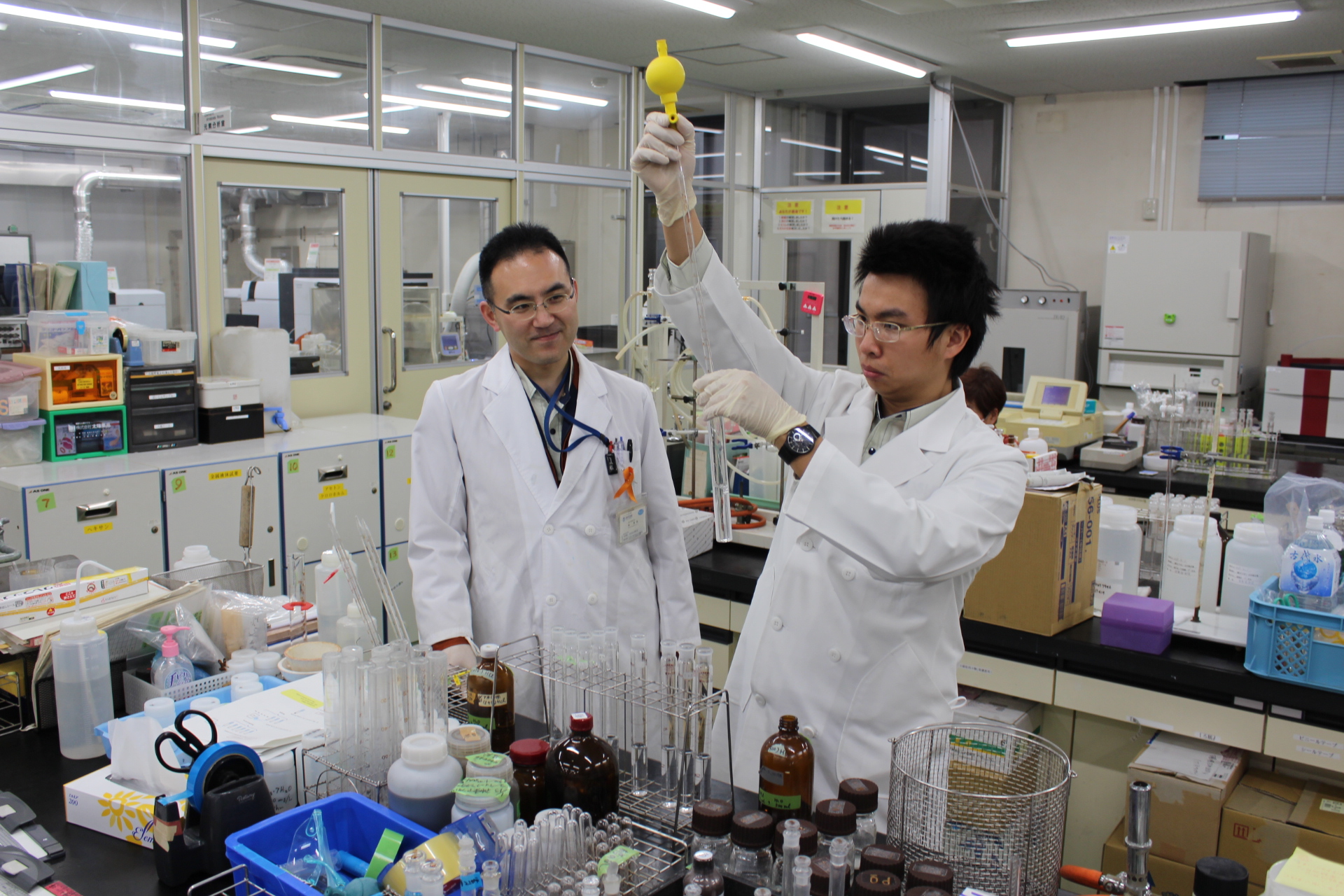
1955年に創業した当初は生活廃棄物の収集・運搬などを行っていましたが、社会問題が「衛生」から「公害」に、「公害」から「環境・生態」に、「環境・生態」から「共生」へと移り変わる中で、社会課題の解決のため次々に法規制が整備されました。その法律の中に当社は市場(新たなビジネスマーケット)を見出し、必要な有資格者を保有し許認可を取得してまいりました。社会のニーズが現在の日吉を育て、『環境ソリューションカンパニー』へ導いていただいているという想いがあります。そのため、取り立ててSDGsを始めたという意識はなく、当社の行ってきたすべての仕事が、SDGsに結びついたと考えています。
最近では、様々な中小企業がSDGsに取り組もうと、やや無理をされているように見えることがあります。企業は社会から必要とされているから存続しています。当社は第一回渋沢栄一賞を受賞しておりますが、渋沢が示した「論語と算盤」は、当社の考えや活動とも合致しており、それこそがまさに、無理なくSDGsの取り組みを行うことにつながるものと思います。
SDGsに取り組んでみて、変化したものは?
多くの方がSDGsを知るようになる中で、社外からSDGsを推進している企業として取り上げていただけるようになりました。一方、社内では、仕事として日頃から取り組んできていることなので、自分たちがSDGsを推進しているという認識に至っていないように思います。
今後は、社員にももっと「自社とSDGsの関係」を知っておいてもらいたいと思います。当社では近江商人の三方良し(売り手良し、買い手良し、世間良し)に“次世代良し”を加えた「四方良し」を実践しています。一例として近隣小学校でごみ収集の出前授業を行っていますが、こうした取り組みが子供たちの環境に携わるきっかけになっていると、参加することで改めて気付く社員がいます。「自分たちの日頃の仕事がSDGsに貢献している」と多くの社員が認識することが、企業としての存続と成長にもつながると思っています。
今後の方向性を教えてください
当社はこれまで「水」を軸に環境分野で事業をしてきましたが、今後は今までの取り組みを続けながら、国内外で最重要課題となっている脱炭素分野にも取り組み、存在価値を高めていきたいと考えています。
更には、検査ビジネスのオンライン化も一層推進したいと考えています。遠隔地から分析すべき物質のサンプルを送ってもらい、インターネット上で分析データを報告し、過去の分析結果も集計やグラフなど見える化しデータで保管する。こうした取り組みを普及させることでペーパーレスにも貢献できます。
当社の担う「人の生活と産業の最適化」を支える仕事は、これまでもこれからも変わらないので、それを通じて地球温暖化対策に貢献できればと思います。
あなたの目指すSDGs2030年はどんな姿ですか?

株式会社日吉 村田社長
性別や国籍、LGBTなど関係なく、多様な人材が自然に社内で仕事をしていることが当たり前の姿になれば良いように思います。「女性活躍」と言われるからと、ことさらに女性を押し上げるのではなく、女性や男性を分けずに、自然体で十人十色の社員を適材適所で受け入れられる社内環境にしていけると良いですね。
また、当社は海外の方と多くの交流を持っていますが、発展途上国における大学生のSDGsの認知度は、さほど高くはないように感じています。引き続き「環境」を通じた人材交流と育成を行っていきますので、その中で、海外の大学生にSDGsの認知度を高めるように取り組んでいきたいです。それには個社での活動に加えて地域や業界団体等の有志で、実のある産学連携に取り組みたいと考えております。
|
環境サービス事業を展開していた同社では、SDGsを意識せずに取り組んできたボランティアが新たなチャンスを生み出し、海外市場を取り込むことにつながっています。 これから取り組む企業に対して、「無理にSDGsに取り組むのではなく、ライフサイクルの見直しから始めてみると良い」と示唆してくれました。企業は日頃から経営改善に努めている。その中からSDGsにつながる芽があるのではないでしょうか。(2022年1月21日) |
2.このページに関するお問い合わせ
近畿経済産業局 総務企画部 2025NEXT関西企画室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6003
FAX番号:06-6966-6073
メールアドレス:bzl-kin-kansaikikaku@meti.go.jp
