トップページ > 施策のご案内 > ものづくり産業支援 > 関西ものづくり新撰 > 新撰エモーショナル > 株式会社ムラタ溶研
薄板金属溶接の自動化と材料薄型化対応 電子部品の大量生産を技術で支える
~株式会社ムラタ溶研~
最終更新日:令和5年3月15日
ムラタ溶研は金属溶接に自動化と薄板化の変革をもたらしている。主力の接合装置「フープウェルダー」シリーズでは最薄で厚み35マイクロメートルの材料を接合する機種や、加工ラインで前後の機械と同期運転できる「完全自動化ロボットタイプ」を業界に先駆けて市場投入した。

完全自動化ロボットタイプの「NFW-500TA」
精密化が進む電子部品業界では、高い品質要求に応えて安定供給するため、すでに加工は人の手に頼れない領域に入り込んでいる。ムラタ溶研はこれを見据えて自動化装置の開発を進め、溶接の新世界を切り拓いてきた。溶接職人だったからこそ、手溶接の限界を知る。「匠の世界と決別」した創業者の村田彰久会長は「自分は溶接を捨てた人間」と語る。
フープ材接合の完全自動化でプレスライン効率化
モーターコアや半導体のリードフレーム、コネクタなどの電子部品の生産には、薄板金属がコイル状に巻かれたフープ材を用いる。フープ材はアンコイラー(繰り出し機)からプレス機へ高速で自動供給され、大量の部品へと姿を変える。
一方で1巻きのフープ材が底をつけば、装置を止めて新品に交換しなければならない。この停止時間はプレスラインのボトルネックだった。これを解消したのが、ムラタ溶研のフープ材接合装置だ。供給中のフープ材と未使用のフープ材の末端同士を溶接し、連続供給を可能にする。
接合装置は二つのフープ材を把持(クランプ)して、端面をきれいに切断し、付き合わせて溶接する。さらに溶接後の肉の盛り上がりを滑らかにすると同時に金属組織を強める圧延などの工程も内部で完結させる。
ムラタ溶研は人によって作業の質にばらつきが出るデリケートな工程を接合装置で段階的に自動化してきた。「クランプ」は最後に残った未自動の工程だったが、2020年に開発した「完全自動化ロボットタイプ フープ材接合装置 MFW―500FTA」で一連の流れをすべて取り込むことに成功した。
MFW‐500FTAは、IoT(モノのインターネット)化によってプレスラインの各種機械と同期運転を可能にした機種。顧客であるデンソーとの共同開発で、使用中のフープ材が終了する信号を受け、アンコイラーとプレス機の間に移動して自動接合を始める完全自動を実現した。

ワークの引き込み、取り出しを自動で行う
「画期的な技術もユーザーに受け入れられなくてはイノベーションと呼べない」と考える村田会長は、シンプルでコストを抑制した設計を志向する。一般的に、ロボットと言えば、ヒューマノイドや産業用の多軸ロボットが連想されるが、MFW―500FTAでは前後の素材ハンドリングでそれらを採用せず、装置自身が移動し、内部に組み込んだピンチロールが素材をキャッチする仕組みを考案した。
高速化するプレス 危険領域に人を入れないライン設計へ
「ユーザーの現場でしか開発の種は生まれない」(村田会長)。ムラタ溶研は、効率化や品質安定化といった製造現場のニーズを元にフープ材の接合工程を自動化してきた。完全自動タイプ「MFW‐500FTA」が生まれたのは、長年のユーザーであるデンソーからもたらされた新たなニーズがきっかけだ。デンソーは電磁鋼板を打ち抜いてモーターコアを生産するラインを効率化するだけでなく、現場の危険領域へ人が入るリスクをなくすため、完全自動化を目指していた。
プレス機は年々、高速化している。大量生産分野で使われるプレス機は、いまや毎分4000ショット。最高クラスのプレス機は毎分6000ショットに達する。これに伴い材料供給も高速化。「金属の薄板は触れれば切れるナイフ」と、村田会長も認識する。「この分野は溶接と自動化の両方の技術を理解するムラタ溶研にしかできない」との自負もあった。接合装置部分はムラタ溶研が自由に設計し、後に外販も可能にするという条件で開発を受けた。
今回の開発に限らず同社は大手メーカーとの共同開発が多く、いずれも取引関係が長く深いことから、他社に取って代わられないオンリーワンの地位を築いていることがわかる。その秘訣は知財。「特許を固めていないと、我々の規模の会社なんて吹けば飛ぶ存在だ」と村田会長は、競合他社を追随させない戦略の重要性を指摘する。同社の特許は約60件。中でも業界で注目されるのは、TiG溶接の薄板対応の限界を突破するきっかけとなった「狭窄ノズル」だ。

ズレのない接合を実現
TiG溶接は一般的な素材に対して高品質な仕上がりを実現するが、かつては、遅い溶接スピードや、電極の消耗、アークが風の影響を受けやすいという弱点があった。このため、欧米など海外では極薄板の精密溶接では信頼性に欠けると判断され、レーザーやプラズマといった高価な溶接装置の導入が進んでいた。
だが、ムラタ溶研が2011年に大阪大学接合研究所と実用化した狭窄ノズルはこの流れに一石を投じた。電極棒の周りに円筒形のノズルを取り付け、ガスの流れを制御することでアークの直進性とエネルギー密度の向上、電極消耗の低減を実現。それまで既存技術の延長では板厚100マイクロメートル未満の溶接は困難と言われていたが、いまや35マイクロメートルに対応できるまでに進化している。コア技術である狭窄ノズルの知財では「周辺特許まで抑える」ことで守り、安価なTiGで極薄板が溶接できる唯一のメーカーとして存在感を示し続けている。
AIの搭載と30マイクロメートルへの挑戦
手動機や半自動機も含めたフープ材接合装置のシリーズ「フープウェルダー」の2021年12月期の販売は70台(前期比2.3倍)となる見通しだ。完成した完全自動化タイプ「MFW―500FTA」は、効率化や安全のニーズが高まりから複数の自動車メーカーやモーター関連メーカーから引き合いが相次ぎ、加えて、コロナ禍で製造現場の出勤を抑えたい企業からの無人化ニーズも顕在化している。村田会長は「来期は合計100台に達する可能性がある」と手ごたえを強めつつ、早くも次のイノベーションを模索する。
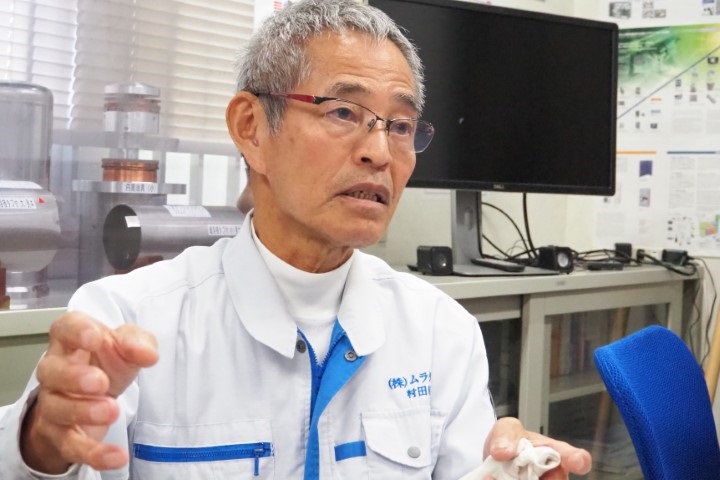
誰もが簡単に溶接できる装置を目指すと、村田会長
創業以来掲げる開発のテーマは「誰でも簡単に溶接できる自動装置」。中でも「簡単に」は、「より簡単に」を繰り返す終わりのない目標だ。現在、開発に着手しているのは人工知能(AI)の搭載。村田会長は「溶接は材料種が多く、これに板厚種の数を掛け合わせると膨大な数」であることから「だからこそAIに向いているし、搭載すれば電流やスピード、電圧、アーク距離など溶接条件パラメーターの設定は飛躍的に簡単になる」と見る。材料の薄型化対応では2020年内に、さらに薄い30マイクロメートル技術へめどをつけ、競合他社の追随を許さない領域を目指す。
経営者メッセージ
これまで世界のモノづくりは人件費の安い国、より安い国へと移管されてきた。しかし恐らく、これからは変わってくる。製品が精密になればなるほど人の手による作業は困難になり、人が介在することによってヒューマンエラーが必ず起きるからだ。ものづくりが自動化でリードする先進国に回帰する動きは既にそこかしこで始まっている。
自動化ニーズは広く、大きく、多種多様だ。当社は現在、サプライヤーにおけるアセンブリー工程を拡大しており、開発・設計と、品質管理に重きを置いたファブレスに近いメーカーへと変貌している。社内の頭脳と、サプライヤー技術の結集で、最先端のニーズに応え続ける。
企業情報
▽企業名=株式会社ムラタ溶研
▽代表取締役社長=村田 倫之介
▽所在地=大阪府大阪市淀川区木川東4-6-11
▽設立=1984年5月
▽売上高=約3億7000万円(2020年12月期)
▽従業員=9人
このページに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6017
FAX番号:06-6966-6080
メールアドレス:bzl-kin-shinsen@meti.go.jp
